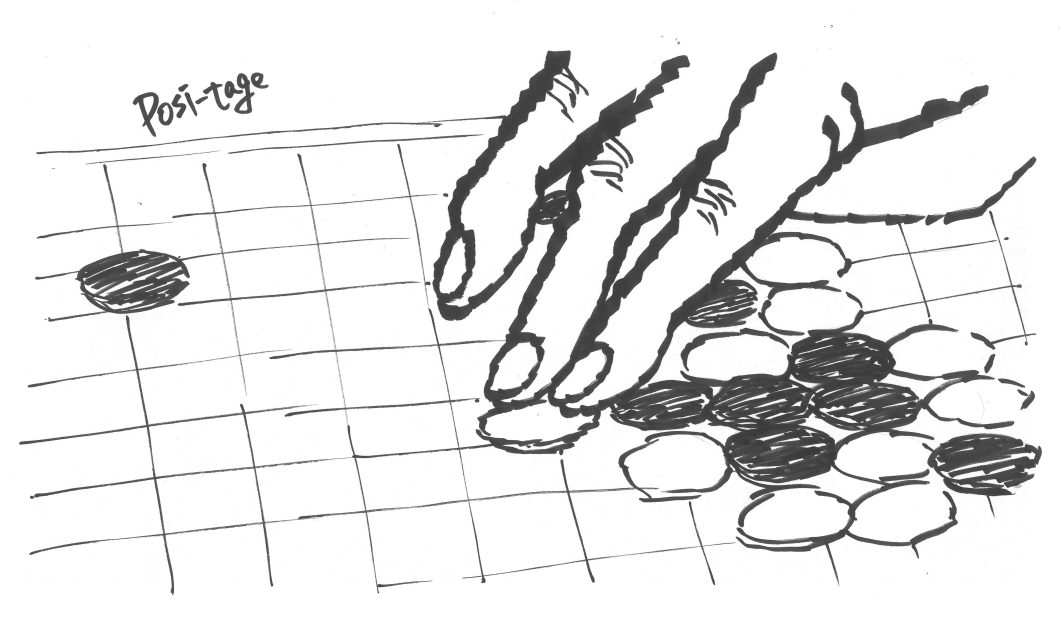出社させたい会社と出社したくない個人
ワークスタイルに関するニュースに目を向けると、海外を含め出社回帰の風が吹いています。週に数日はオフィスへの出社を求める企業とフルリモートを希望する働き手がせめぎ合っている。企業側からすれば、偶発性の欠如による「イノベーションの阻害」、コミュニケーション不足による「チームの結束力低下」、「単純な作業生産性の悪化」、リモートでもちゃんと働いているかを管理する「余計な業務の増加」、業種業界によっては「情報セキュリティーの強化」など理由は複数あると思われます。(※業績が良ければ、ある程度まで目を瞑ることもできるんでしょうけど…)
一方の働き手はというと、在宅に慣れてしまった今、身だしなみを整えたり、オフィスへの通勤、業務以外のやりとりなどが「シンプルに面倒くさい」ということなのでしょう。でもさ、毎日会社に行っていた時代と比べれば・・・と思ったりもしますが、やはり「〇〇しやすさ(=ラクであること)」への欲求には際限がなく、一度それに慣れてしまうと変化に対して抗いたくなるものなのかもしれません。
働き方とオフィスの変遷
まだコロナ前の2019年、浜松町にあるビルの共用部をリニューアルするプロジェクトで働き方とオフィスの変遷について振り返ってみたことがあります。1970年代~1980年代前半の高度成長期は、ソロバン、タイプライターなど手作業による事務処理が中心でした。ヒエラルキー型の組織図をそのまま再現したような学校式レイアウト。その後、オフィスコンピューター、電卓の普及が進み事務処理は大幅に効率化が進む。オフィスは島型対向式レイアウトが主流となるが工場式マネジメントが主流のまま。
1980年代後半~1990年代初頭のバブル期は、急激な経済膨張によって人手不足が問題に。オフィス人員増加も急加速。競争の激化により各企業は付加価値づくりが求められました。深夜残業の常態化によるストレス増大や、OA化によるワークスタイルの変化に対応し、オフィス環境の整備が課題に。家具の色は明るいアイボリー系に変化し、パネルやフロアカーペットの導入など、インテリア意識が高まる。食堂やリフレッシュエリアの充実も見られた。
1990年代~2000年代はマイナス成長期。バブル崩壊によって、「変化し続けないと生き残れない」という時代へ。企業は体質改善を求め、ワークスペースの効率向上や組織変更への柔軟な対応など、オフィスコストの削減を中心にオフィス見直しを徹底して図る。一方、ネットワークPCが一般化し、携帯端末を使ったモバイルワークが出現。働き方の多様化に伴い、オフィスレイアウトのみならず働く場所そのものも多様化していく。 現在の働き方とオフィスもこの延長線上にいるような気がします。
グラデーション、そしてマーブルへ
今では当たり前のテレワーク、その歴史は意外と古く1984年だそうです。普及までは至らなかったようですが、出産・育児を理由に退職する女性の離職防止や郊外に住む社員の通勤負担を解消するためにサテライトオフィスの設置がテレワークのはじまりと言われています。1990年代に入るとポケベルやPHSの普及、2000年以降は携帯電話やパソコンが一気に家庭にも浸透していきます。オフィスの外でも仕事をする人が増え、働く場所と生活の場の境界線がゆるやかになっているグラデーション化が進みます。
2010年代はスマートフォンが登場。パソコンを持ち歩き、カフェで作業するシーンが日常になります。業界や企業によりますが、働く時の服装もだいぶ自由になっていきます。一見すると、プライベートなのか働いているのか分からない人や景色が当たり前に。会社の上司から「明日までにこれやっておいて」とLINEで業務の指示を受けたかと思うと、同じタイミングで妻から「帰りに牛乳買ってきて」と家庭の指示を受ける。両方の返信をオフィスで堂々と行うことにすっかり違和感は無くなってきています。逆に、家族旅行中に「これはあの案件でつかえる!」と仕事のよきリファレンスに出会い、喜び勇んで同僚に連絡してしまうこともあります。グラデーションを越えて、仕事とプライベートがマーブル化している感覚を皆さんもお持ちになっているのではないでしょうか。
職場には逃げ場が必要
話は浜松町のプロジェクトに戻ります。当時スマイルズが行った共用部の提案は「ちょっとだけサボれる場所と言い訳をつくってあげましょう」というものでした。なぜなら一階にあったスターバックスがビルの建て替え工事の都合でなくなってしまうと聞いたからです。オフィスワーカーにとってのスターバックスは「コーヒー買ってきます」と言って、合法的?(別にコーヒー買い出しは違法じゃありません)に仕事を抜けることができる場所だったからです。つまり、コーヒーが無くなって困るのではなく、「ちょっとサボれる場所と言い訳」が無くなることが問題なのです。
スターバックスだけではなありませんが、このような逃げ場(retreat)や隠れた小休止(hidden break)の価値を侮ることはできません。コンビニや喫煙所も同じ役割を担っているでしょうし、天気のいい日に散歩に出る行為も同様です。かく言う私も一度だけ、どうしてもリフレッシュ(心身ともに)したかった夏の日、ランチの代わりに近くの銭湯へ行って一風呂浴びてきたことがあります。周りに悟られるように、入浴後には髪型もちゃんと整え直しました。
名付けて「ポジタージュ(Posi-tage)」
このような業務上前向きなサボりを「ポジタージュ(ポジティブなサボタージュ)」と命名しましょう。とろみのあるスープみたいですが、なかなかいい言葉ではないでしょうか。ポジタージュはカフェがある、喫煙所がある等のハードも必要ですが、それ以上に寛容さ、曖昧さ、柔軟さ、適度なルーズさといったソフト(組織の理解)が重要です。「あれはOKで、これはNG」のように、ルールにしたり、それを管理しはじめると結局息苦しくなってしまうため、マネジメントは難しいと言えます。多少のことは大目に見る適切なテキトーさが肝要です。
また、あくまで息抜きでなければなりません。悪意のあるサボり(仕事をしないだけ)は望むところではありません。会社に価値をもたらさないどころか、自分の時間も無駄にしてしましますので、これはオススメしません。(少なくとも、スマイルズでそれをやる意味は皆無ですね・・・)
ポジタージュは生産性に寄与するらしい
持論を肯定するようなトピックスを二つほど紹介します。一説によると、英国コーヒーハウスがオフィスの始まりらしいです。オフィスの会議室で、決まったアジェンダを決まった時間で進行する会議からはユニークなアイデアや新しい事業のヒントは出てきにくそうです。カフェでコーヒーを飲んでいるくらいのリラックスしたモードとシチュエーションが発想にはちょうど良いのでしょう。
18世紀のイギリスでは、作家たちが街中のコーヒーハウスに集って仕事しており、コーヒーハウスがオフィスとしての役割を果たしていました。コーヒーショップの店主の多くは店舗の上階に住居を構えて、数人の家事手伝いを雇って暮らしていたそうです。
他にも、マサチューセッツ工科大学がこんな研究結果を発表しています。
仕事中にTwitterやFacebookをチェックしたり、ネットの記事を読むことに罪悪感を覚えている人にいい知らせがある。新たな研究によれば、作業中にサボる時間を少しだけ入れることが、仕事の生産性向上に役立つ可能性があり、とくに仕事の中味が退屈であるほどそうした傾向がみられる という。
この研究は、MITのHumans and Automation Lab責任者であるメアリー・カミングスが行ったもので、参加者にコンピューター作業を行わせ、その生産性を計測。高い生産性を記録した人の多くは、4時間の実験のうち最大で30%ほどの時間をほかの目的に使っていたそうです。「ラジオを聞いたり、会話をすることを禁じたり、休憩を制限することは仕事中の退屈につながり、生産的な業務環境の構築につながらない」という結論も出されたとか。
ココに、ココロがあるから
管理する側からすれば、一切の無駄が無く、労働時間目一杯に、なるべく沢山のことをやってもらった方が理論上のベストスコアに近づくのかもしれません。No No、私たちはココロを持った人間です。日によって調子の波があって、人によってペースはバラバラなわけです。それを一律に、恒常的に、無機質にマネジメントするなんて、そっちの方が理屈に合わないわけです。気持ちよく頑張れる状況を、自分のココロに聴きながら、ワークとライフのバランスを取りましょう。そして、程よくサボリも入れながら。明日はどんなポジタージュをしようかな。
PROFILE
吉田 剛成(よしだ たけなり)
株式会社スマイルズ 取締役/CHRO
2008年スマイルズ入社。Soup Stock Tokyoでの店長業務、人事部採用担当を経て、2013年から2015年にかけては、スマイルズの交換留職で経済産業省クリエイティブ産業課へ出向。中小企業の海外展開事業や海外向け情報発信の立ち上げに参画。現在は外部案件のコンサルティング、企画・プロデュース、ワークショップなどを担当。取締役として組織づくりや事業企画にも関わる。時折ダジャレや韻をベースとしたコピーライティングも手掛ける。大きな声では言えないが姑息さを兼ね備えたプロジェクトマネジメント術にも定評がある。週末は息子のサッカークラブサポーターが趣味。