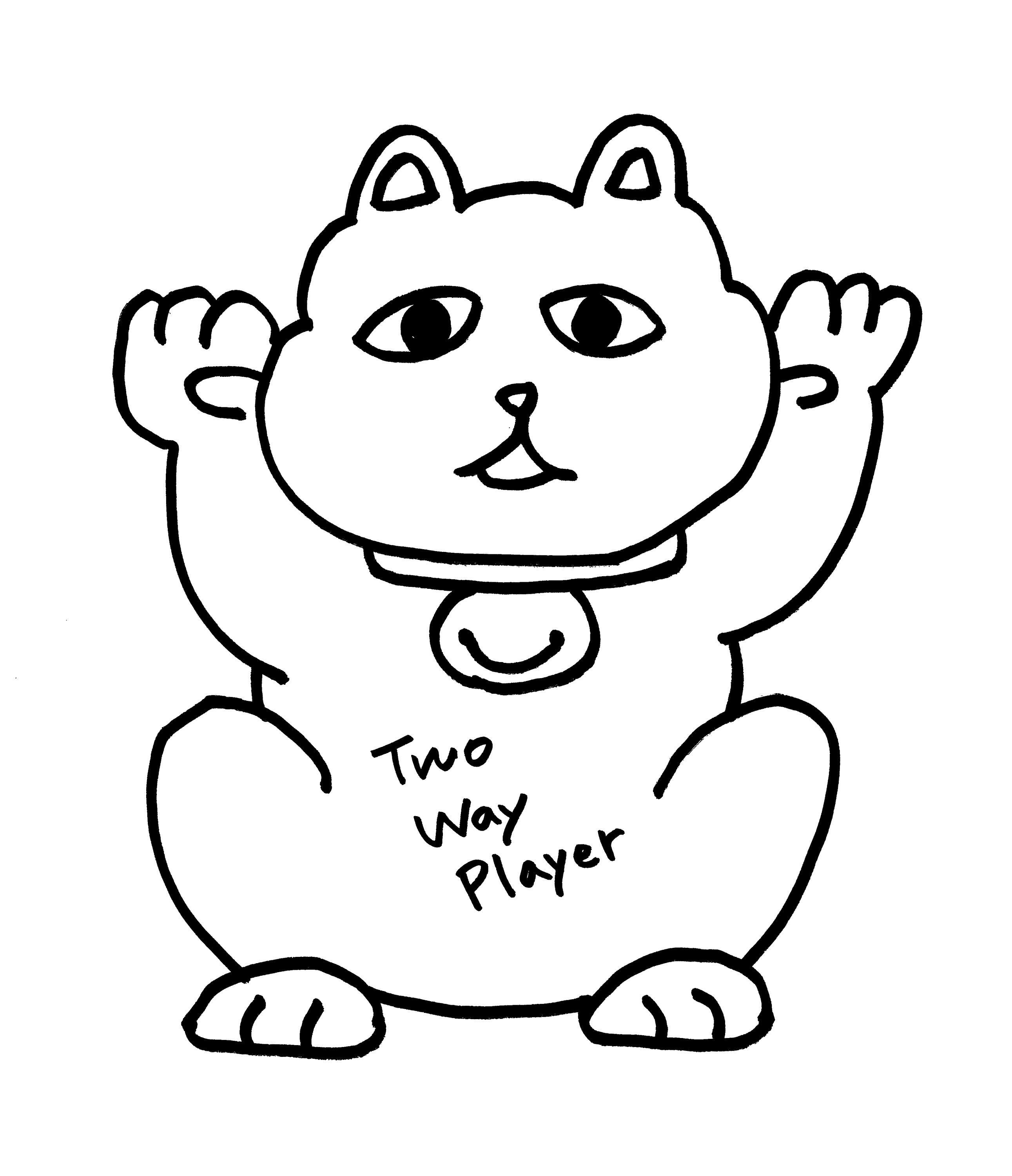「変わりたい」という共通課題
実は最近、組織開発系のご相談が増えています。業態プロデュースや新ブランド立ち上げ案件のように対外発信ができないのですが、実は結構やっているのです。経済状況も社会環境も労働市場も手厳しい昨今、問題・課題のない会社はないでしょう。「既存事業だけでは成長に限界がある」「なかなか新しい事業が生まれない…」「組織カルチャーを変革したい!」といった声は方々から聞こえてきます。「このままではいけない」という共有の問題意識はある。しかし、どうやって、既存の事業を維持しながら新規事業でイノベーションを起こす、のか。ここで思い出されるのが、『両利きの組織をつくる(英治出版 , 2020)』です。
組織が進化するためには、異なる二つの組織能力が必要とされる。ひとつは「(既存事業を)深掘りする能力」(exploit)であり、もうひとつは「(新規事業を)探索する能力」(explore)である。両利きの経営とは、企業が長期的な生き残りを賭けて、これら相矛盾する能力を同時に追求することのできる組織能力の獲得を目指すものだ。
《参考文献》
加藤雅則 , チャールズ・A・オライリー , ウリケ・シェーデ. 両利きの組織をつくる. 英治出版, 2020, 003p.
ふむふむ、確かにその2つの能力を組織が有していれば理想的な事業展開が叶いそうな気がします。そして、続くページにはこんなことが書かれています。
既存事業と探索事業の両立に伴う「矛盾」を引き受けるリーダーシップ(意志表示と価値判断)を経営者に求めることになる。この矛盾の中にこそ、独自性が生まれるのだ。(025p)
両利きの組織には、両利きの経営者が必要では?
なるほど、確かに経営者の理解がないと、その意思決定や寛容な承認はなされないなとアタマでは分かりつつ・・・だいぶ、経営者の性質や力量に依ってくるなと(悩)。文章にするとシンプルに見えるものの、体現するのはめちゃくちゃ難しいやつです。相反する思考や姿勢、トレードオフな判断や意志決定を行いながら、チームを納得させ、実行を促すという、高難度要求の矢が経営者の背中には突き刺さっている。これは私の勝手な仮説なのですが、経営者自身が両利きや二刀流であれば、生じる矛盾を過去の経験的に理解でき、肌感覚をもって矛盾を受け入れることができるのではないでしょうか。
二刀流はスポーツだって、ビジネスだって
二刀流と言えば、やはり野球の大谷翔平選手が思い浮かびます。投手としても打者としてもMLBトップクラスで戦う彼は、説明不要な世界的に特別な存在ですね。2020年に「投手としてシーズン20イニング以上に登板」「打者でシーズン20試合以上に出場、または60打席以上」の両条件を満たせば、「TWP(Two-Way Player/二刀流選手)」として登録できるという新しい制度をつくるキッカケになっており、まさにMLBという組織カルチャーを変革してしまっています。
大谷選手は本当にすごい、すごすぎるわけですが、ビジネスの世界にも二刀流で新たな道を切り拓いた経営者が存在すると思っています。任天堂の社長を務めた岩田聡さんは、優れたゲームクリエイター・プログラマーであり、誰もが知る任天堂というグローバル企業の経営者でもありました。堤清二さんは、辻井喬の名で小説家・詩人として活躍しながら、西武百貨店・パルコ・無印良品をはじめとするセゾングループを率いる経営者でもありました。定量的な目標よりも、顧客の「気分」や「文化」に重点を置き、ビジョンや美意識を大切にした「感性経営」は、文化人であり経営者であった堤さんだからこそ成し遂げられ、かつ説得力を持ち得た方針ではないでしょうか。他にも、高畑勲さん・宮崎駿さんという稀代のアニメーション監督が舵取りをしたスタジオジブリも、クリエイターが船頭として組織体制や事業展開を模索していったために今の姿があるように思えます。
自社事業とクライアントワーク、どっちもやるが最善です
上記の名だたる方々と比べるのもおこがましいですが・・・私たちスマイルズも両利きや二刀流を意識しています。自分たちで企画・投資・運営を行う「自分事業」とコンサル・プロデュースで関わる「クライアント業」この両方が持ちつ持たれつの状況を大切にしています。自分事業で培った実業知はクライアント業で有益な情報や与信になってくれますし、自分事業で出来ることはリソース(人的・金銭的)に限りがあるためあれもこれもは出来ませんが、クライアント業では自分たちの事業範囲を超えた価値提供が可能になります。そこで得た経験やネットワークを自分事業に還元する。また自分事業では実験的なアプローチを試みて、それをクライアント業へ還元するといったサイクルが理想です。
創業者の遠山も現社長の野崎も、アートやデザイン、クリエイティブが大好き。先日遠山はポッドキャストで「仕事というキャンバスで絵を描いているようなもの」と表現しておりましたが、ビジネスというフィールドで創作活動を続けているような経営者ゆえに、このような事業戦略の選択や経済合理性を第一義にしない経営方針に至っている気がします。
これからは、みんな二刀流の時代?!
果たして経営者が二刀流であれば組織は上手くいくのでしょうか。うーん、どうでしょうか。どこまで経営がマネジメントしても、コストを切り詰め利益確保に勤しむ部署と可能性を探しR&Dに投資する部署の対立はなくならないような気がしてなりません。(というか、その状況をひたすらイイ感じにする経営業務が大変そうでなりません;)
乱暴論ではありますが、「これからはみんなが二刀流になっていく!」と想像してみたいと思います。担当者同士も二刀流であれば自分の身に覚えがあって、それぞれの事情も心情もわかるので対立が起こりそうな時に、融通しあえたり妥協ができたりする。また個人の興味関心やキャリア形成の観点でも、あれもこれも出来ることはチャンスや魅力として捉えられる。二刀流メンバーが増えれば個人の守備範囲は広がって、組織としてのカバー範囲やサポート体制も強化されるのではないでしょうか。
実際に、スマイルズには料理人兼プロジェクトマネージャーの人やプロジェクトディレクター兼フォトグラファーをはじめ二刀流人材が数多く在籍。また副業含め四刀流の阿修羅状態?!な広報もおります(笑)
二刀流でも、二足の草鞋でも
外部に目を向けてみると、新しい世代では二刀流が当たり前という価値観も垣間見えます。バンドに入りミュージシャンをやりながら大手ゲーム会社でマネジメントを務める方がいたり、地域資源の再生プロジェクトや戦略投資の会社に勤めながら仲間とクリエイティブユニットで展示や空間デザインを手掛ける方も。
彼らに共通する印象的な点として、同時期に二刀流であることがあげられます。20代はスポーツ、30代は実業家、40代は投資をやる、といった漸次的に他の事に取り組むのではなく、現在進行形で二つ三つの顔を持っている。また、それに対して特殊な在り方だという認識を持つではなく、ナチュラルに二刀流であることです。この価値観はこれからより一般化し、会社が求める人材の要件にも影響してくるように思います。
会社に所属すると決められた部署で決まった業務があてがわれ、名刺には一つの定められた肩書が記されて、一つのことに集中して腕を磨くことが推奨される空気感に満ちているように感じている人も多いでしょう。しかし、遡れば江戸時代から「二足の草鞋を履く」という言葉があるように、二刀流であることは私たちの社会にありふれていたのかもしれません。わたしもHRという刀を握り始めましたが、まだまだ振るうには心持たない…一日も早く二刀流と呼べるように精進します。今回はこの辺で。
にっちもさっちもいかないならば
あっちもこっちも、どっちもやってみるのはどうか
あれもこれもは中途半端に非ず
あれもこれもが最善の選択肢
あれもこれもを招き入れる組織
PROFILE
吉田 剛成(よしだ たけなり)
株式会社スマイルズ 取締役/CHRO
2008年スマイルズ入社。Soup Stock Tokyoでの店長業務、人事部採用担当を経て、2013年から2015年にかけては、スマイルズの交換留職で経済産業省クリエイティブ産業課へ出向。中小企業の海外展開事業や海外向け情報発信の立ち上げに参画。現在は外部案件のコンサルティング、企画・プロデュース、ワークショップなどを担当。取締役として組織づくりや事業企画にも関わる。時折ダジャレや韻をベースとしたコピーライティングも手掛ける。大きな声では言えないが姑息さを兼ね備えたプロジェクトマネジメント術にも定評がある。週末は息子のサッカークラブサポーターが趣味。